司法予備試験に参戦して、最初のハードルとなるのが「いつになったら起案できる?」という問題。上手く書きたいとかA判定をとりたい以前の問題として、そもそも【いつから初歩的な答案練習ができるのか?】多くの受験生が通るであろう「論文書き始められない」問題について独断と偏見で語ります。
論文っていつになったら書けるようになるの⁉
こんにちは~予備試験受験生の管理人です。とつぜんですが皆さん、起案してますか?「起案」と呼ぶにせよ「答案作成」と呼ぶにせよ、避けては通れないのが論文対策です。
書けども書けども合格答案にいきつくまでが長いのですが、それ以前に…「そもそも、どうやったら論文を書けるようになる?」というお悩みって大きいですよね。
1年目の最大の悩み
どう書くか、どう対策するか、論文式試験に関する情報はさまざま溢れているのですが…
そもそも、「いつ」「どうしたら」「論文が書き始められるのか」という超超超初歩レベルの悩みって、最大級の問題なのにも関わらず情報が少ない気がしています。書いた物の良し悪しの論評や、全般的な対策のハウツーは流れている。が、この手前の手前の手前レベルの情報がほしい。
最低限書ける人がより良く書ける方法じゃなくて、ぜんぜん書けない人が書き始められる方法が知りたいって思う時ありません?
起案初心者の状態
まず手を動かそう、何か書いてみようと言われて、なんだかんだとやってみてもピンとこない。
短文事例問題を解いてみる。う~ん、論証が暗記できてなかったから、イマイチ正しいことを書けていないみたい。何問かそれっぽく書けても…短文事例問題って、実際の論文試験とぜんぜん違うでしょ?
過去問を見ると…む、難しい!参考答案を読んで、がんばってそれと似たようなことを書いみたところで…え~~時間かかりすぎるし文章ぐちゃぐちゃ。もうこれいっそ写経で良くない??
演習書の問題を見ても、1文字も書くことが思いつかない。じゃぁ基礎学習に戻ればいいのかな?やっぱり短文事例問題をつぶすべき??でもそれじゃ力つかないって誰かが言ってた気がする!
この辺りで無限ループに陥り、ゆうに1年2年が経過。これ、受験生あるあるじゃないでしょうか?
そもそもフォーカスされない件
一通の答案を、一応書くことができる状態になるまでが長い。でも、この状態の受験生に対するアドバイスって、すごく少ない気がしています。
このフェーズがほとんどフォーカスされてないといいますか、シカトされている気がするのは私だけでしょうか?
予備校の論文講座は乱暴に言ってしまえば「初学者は何をすればいい?」「(中略)」「どうしたら合格答案が書ける?」…みたいな⁉ (え、中間どうなった!??)(※個人のもつ感想です)
合格者の「こうやって書けるようになります」も…う~んサンプル数1だし、やっぱり「起案を始めたいけどなかなか始められない時期」については端折られていたり。
端折られてるのか…はたまた、合格者は悩まず最初から起案スタートできてたのか…というくらいピンポイントの情報が少なく感じます。
もちろん、起案を軌道に乗せるまでの取り組みって人それぞれで諸説もあり。なにかと混乱してしまいます。
魔の下積み時代?
この「起案手前」のフェーズは、強いて言えば「インプット期」とか「基礎学習期」と呼ばれます。まずは1周!全体像をつかみましょう!というアドバイスがつきやすい。
それか「君はまだ書いていないだけ」的な扱い。バンバン演習に入って行きましょう!短文事例問題を解いてみましょう!
そして1科目50以上の短文事例問題と向き合いつつもその物量につぶされ、ある方向からは「さっさと過去問にうつれ」という情報が舞い込んでくる…。それで結局、前述の無限ループに陥るわけです。とにかく手を動かせども動かせども書ける気がしな~い!!
起案以前の対処法が少なさ過ぎる
私は先生方の教えを…自分で言うのもなんですが、わりと実直に守ってインプット学習と並行して演習に取り組んできました。基礎講義を聞くのと並行して、短文事例問題と過去問にも目を通しました。見よう見まねで起案もしたし、その見まねの起案ができないときは写経もしました。
なのですが…この名前のつかない下積み時代は長かったし、この期間に有効なアドバイスってなかった、という実感があります。
そう感じるのは私がある一時期を境に急に答案の形で書くようになり、それ以降に目を通してきた解説という解説が「これ最低限は書ける人向けの情報じゃん」と思うものばかりだからです。
もちろん全ての先生方の解説に目を通したわけではないので「え、そのあたりちゃんと解説されてるよ?」というツッコミがあったら生暖かく見守っていただきたいのですが。
なぜ答案が書けないの?
とにかく、どうしたら答案というもの、論文というものが書けるようになるわけ?…という切実な悩みがあります。まず最低限でも書けるようになりたい…と思っていたとき。
私の場合、一番のハードルは「自分の頭で文章を考えて、書く」という体験がぜんぜん踏めなかった点にありました。
書いても書けない
このお悩みを抱えている人なら、同じだと思います。全く手を動かすつもりがないわけじゃなくて、もちろん短文事例問題なり、論証なり、紙に書いてる。でも昨日暗記した論証をそのまま紙に書けただけで「ヤッタ~じぶん論文書けた~」って気になりますか?なりませんよね。
本やネットに掲載されてる「答案の型」みたいなものを脇に置いて、一行ずつそれに従って書いてみたら…。これは暗記の吐出しよりちょっとマシ。でも…それでも、それだけでは「自分は起案するレベルじゃない」という自己評価のままです
これって個人的には「自分の頭で文章を考えて、書く」という行為ができてないことが最大の問題な気がします。
要は真似して書いただけじゃ何もしないよりはよっぽどいいけど、自信にはつながらない。書いた実感が得られないのです。こんな取り組み方だとアウトプット学習のほとんどの効用が得られないまま悶々としてしまいます。
そりゃ書けないよね…
ここで個人的な話ですが、私は作文・文章の書き方を教える仕事をしています。(え?この文章力で?「意外~」と思った人は今日ちょっと嫌なことありますようにーー!)。その体験を踏まえると、起案って結構な無茶ぶりな気がしています。
作文の指導は小中学生なら教室の机に向って、一行一行、アドバイスしながら進めます。大人の文章指導もPCで同じことをします。だって普通に「ハイ、このテーマで書いてみてください、ホラ書いてよ」って言われて、急に書くのって難しいですよね。
答案書けなくて困ってる。学習初期から個別指導を依頼してる受験生は少ないし、個別指導の先生だって一行一行付き添って指導してくれるわけじゃない。
結局私たちは、独学で書いているのです。これって実は、凄いことじゃないでしょうか?
インプット専念はアリ?
一通の答案を書けるだけですごい、自分はまだ全然そんな段階じゃないから。…なんて感じたりして、いろいろなアドバイスも「自分向けじゃない」と感じてしまったとき。いっそ一定期間「起案しない」と決めて離れるのはアリでしょうか。
あなたの学習計画は?
起案にウェイトをおきすぎないスタンスの受験生も相当数いて、それで結果的に書けるようになる人もいます。ただし、身の回りで見聞きした超個人的印象では、棚上げが功を奏する人ってわりと珍しい気がしています。というのも、学習スケジュール崩壊の危機と隣り合わせだからです。
半年ふっとぶインプット
インプットに専念となると、基本書・レジュメを振り返りつつ、短文事例問題を眺めたりするような学習が定番かもしれません。1科目の1周に何日かかるでしょうか?
学習がある程度進んでいる人なら教材の回し方も上達しているので、数日でパパっと科目を外周できるかもしれません。でも、それができない段階だから悩んでるんですよ!…私自身も特定の科目をきちんと1周しようとすると2週間くらいかかってしまいます。これを10科目でやると…?結局半年くらいはかかってしまいます。論文対策を半年にわたって棚上げしたら、その年の受験は短答だけで満足するのかという究極の選択に突入します。
きっちり行動できるなら
独断と偏見で書いちゃいますが、起案を先延ばしにできて上手くいくのは、勉強時間の確保・管理ができる人。「この時期になったらこう行動する」という計画・決断をしっかりできる人。というのが個人的な印象です。(しつこいですが、あくまで印象ですよ!)
節目のアウトプットがおすすめ
おすすめは、1科目終わった最後に過去問や演習問題を使って、記念起案をすることです。(私はこれを、初回インプットにやってました)。ボロボロでもなんでも良いから一通書いてみる。1科目1周の終わりにそれができなければ、それこそ「いつ書くの?」状態になってしまいます。常に「今でしょ!」が正義じゃないにしても、自分がエイッと行動に移せるかは見守っておきたいですね。
書き始められないときの解決策は?
さて、起案がうまくいかない時の対処法としては次のようなものがあります。
・基礎に戻り科目の全体像を把握しよう
・演習を積み、思考力を身につけよう
・答練を受け、強制的に書く機会を作ろう
このあたりの一般的なアドバイスは的を射てるものだと思います。受験生同士でざっくばらんに語り合うとだいたい出てくるボヤキが上の三つに絡むものだったりします。(「やっぱり俯瞰して見る力は大事だよな~」「それができたら苦労しないですけどね~」…みたいなボヤキ)
書けない理由の自己診断
とはいえ、一般的な対処法で満足して起案を半年棚上げして結局あんまり進歩しないまま一年が過ぎてしまった。…ということは避けたいですよね。
個人的なアドバイスとしては、書けない理由を洗い出すことが大事です。超超超言語化です。
今どんな教材を使って、どんな学習をしているでしょうか?
「短文事例の教材を使って、とりあえず覚えた論証を紙に書いてみて、あてはめを数行書いてみる」とか。「定評のある演習書を買ったはいいものの、全く解けなくて読むだけになってる」とかでしょうか。
書けないって、どう書けないんでしょうか?
問いを見て、そもそもその問いが理解できていないんでしょうか?(例:行政法で「処分にあたるか」という問いが、何を意味するか分かってないレベル)。書き出しがうまくいかない?設問の問いをオウム返ししてとりあえず何かしらの文章を書き始めることはできますか?どこで筆が止まっているでしょうか。
あなたの症状は?
文章の「症状」って本当に人それぞれで個人差が大きいものです。だから自分の事を、”まだ書けてない人の中の一人”って決めつけるのはおすすめしません。
たとえばですね、あれですよ、女同士で「彼氏・夫と上手くいってない」「ほんそれ~」ってわきあいあい喋ってるとするじゃないですか。でもその実態って超超超個人差ありますよね。文句言いつつキャッキャウフフしてる人たちもいれば本気で破局寸前の人もいるし、悩みの質も違ったり。つまり誰かと「答案書けない」「ほんそれ~」って喋ってても人それぞれ全く状況が違うと思うんですよね!
言葉にできない躓き
今やってることを、とにかく言語化・客観視するのはおすすめです。なんだかんだ言って一人ひとり状況と躓きポイントが違います。
世の中には「一言相談してくれたら助けるのに」と思っているめちゃ親切な!そう、神のように親切な合格者・受験生がいるものです。でも、悩みを言葉にできなければそんな潤沢なリソースに一切アクセスできないことになります。「とりま受験情報収集のためにSNSやってます」ってタイプの方はどうでしょうか?信頼できる数名の人が身近にいたとして、「今こういう勉強をしていて、ここで躓いている」って普通のトーンで説明できるでしょうか?
これは自己開示やメタ認知も絡むため、超お喋りタイプの私でさえ「モヤモヤしたまま誰にも相談せず気づけば一か月経過」なんて経験は何度もあります。でも、自分一人で解決できないならどこかのタイミングできっかけが必要です。「うまく説明できないけど」と前置きしてでも、書けない理由を相談するきっかけが。
テーマを見つける
自己診断も何も。ミリも分からなくて一文字も書けない。以上。…という状況かもしれません。それで普通だと思います。貴方が天才受験生でなく標準受験生であれば、過去問も演習書もさっぱり分からない、それが普通です。ぜったいに落ち込まないでください。
その「全ムリ」状態を、もうちょっと具体化したほうが良いです。
たとえば、「刑法事例問題集を買ってみたけど…まずこの問題は正当防衛の話だろうって言うのは想像つくけど、でも具体的な論点ってなると全然わからなくて…」「甲の罪責、乙の罪責…もう何から考え始めればいいのかとか、さっぱりで…」といった具合に。
課題の抽出センス
具体化するとボヤキがお悩みに進化します。「論証は少し覚えたけど論点が想起できない」とか「論証もうろ覚えでとっさに出せない」とか「共犯の問題はまず誰から考えればいいのか」など。悩みは学習法に関するものから具体的な処理手順までさまざまですし、何かに絞る必要はありません。テーマ抽出するのが大事です。あなたの悩み、課題、次の学習のテーマ。自分が取り組むべき課題。世の中、大概の疑問にはアンサーが存在するものです。一番困るのは、効果的な質問を繰り出せないことです。
人に助けてもらうのもアリ
あなたが書けない原因は何なのか。日本語の文章力の問題なのか、気恥ずかしさみたいなメンタルも関係してるのか、理解の問題なのか、知識なのか。テーマ抽出を他人に助けてもらうのも有用でしょう。自分の課題を言語化するのはかなり難しいですし。会話から得るものって大きいですから、私も勉強仲間との会話にかなり助けられて進歩しています。予算がある方は個別指導の先生に依頼するのも良いかもしれませんね。
依存は危険
人に頼ることも有用。ただし、依存や過剰な影響には注意したいです。起案に悩みを抱えているときって、「何と何と何をすれば書けるようになるのか、いっそ誰かに指示してもらいたい」…という心境にならないでしょうか。「こうすれば書ける」が知りたい。だから具体的な解決策が知りたい!
こういう心境のときって「〇〇さんがこう言ったから」」ああした、こうした、って言うことが行動原理になってしまいがちです。そしてちょっと躓くと「〇〇先生のあの説は自分には合わなかった」なんて急に裏切られたトーンで長文ポストを投稿したり・・・?いやいや、そういう受験生にはなりたくないですよね!
アドバイスに納得しない
相談相手もこちらのことを100%理解してるわけではないですし、手探りで有用なアドバイスを出さねばと努力してくださった結果…「法的三段論法ができていない」みたいな一般的なアドバイスで終わってしまうこともあるでしょう。
会話がここで打ち切られると、もらった言葉をどう消化したらいいのか?わりとモヤモヤすることもありがちです。妙な表現かもしれませんが、そこで納得してしまわないこと、も大事かもしれません。法的三段論法ができてない、じゃぁ具体的にどうトレーニングすればいい?それだけに特化して何か練習が必要?どれくらいの時間をかけるべき?
アドバイスはきっかけの一つ
いろいろと検証していくと、「三段論法は日ごろの起案で意識することが大切。慣れるまでは構成メモの時点で確認。特別な訓練は必要ないけれど、都度都度確認。書いたものを誰かに読んでもらって三段論法が崩れてる所を指摘してもらうと良い。三段論法が崩れがちな状況は…」
…と、こんな具体策がうまれたり、「あ、あくまでこういう意味で言ってるのね」と適切なトーンで理解できるはずです。そして実際問題、教える側も人間ですから今回はたまたまこの添削コメントをつけたけど、読み手が思う意味でのアドバイスじゃなかった…ということもあるはずです。一つのコメント、一つのアドバイスだけに固執する必要はありません。
ぶっちゃけて言いますと…答練を受けていると、ここでいう「きっかけ」の一つにすらならない添削コメントというものも存在します。(むしろそれが自然です。)思考を止めないことと同時に、深く考えても仕方ないことは深追いしないのが良いですね。
個別指導はアリ?
大手予備校の答練ではなく、フリーの先生方や個別指導に特化した先生方に依頼することについて。個人的には、予算が確保できて相性の良い先生が見つけられるなら超超超有用だと思っています。特に社会人受験生にとっては、気軽に相談できる勉強仲間を確保…するまでは手が回らないでしょう。ただし、上で書いたように適切なトーンで相談、アドバイス、行動、解決…と繋がっていくまでにはある程度の期間が必要に思います。
世には「あなたの課題をズバッと指摘します!」という先生もいらっしゃるかもしれませんが、文章指導は1回1通だけで判断できないことが殆どです。でも計る指標がないから受験生からすれば、お手頃価格でたくさん赤入れをくれる人なら皆いい先生に見えてしまうかもしれません。返却答案から得られるものが本当にあるか、どんなアドバイスならスッと入ってきて実践しやすいかって、本当に難しい問題で。(私自身も模索中です)。
…ということで、あとで「裏切られた!」なんて気持ちにならないように、誰かに依頼するにしてもイニシアティブは自分にとっておきたいものです。
書けなくて不安?
もう毎日の勉強…インプットもアウトプットももろとも大変すぎる!こちとらライフゼロ!!そんな状況で、落とし穴に落ちないことって本当に重要です。ここまでで(長々)お話した落とし穴は…
・書けない→なぜ書けないのか考えるのも難しい→いったんインプット優先⇒半年ふっとぶ
・書けない→なぜ書けないのか考えるのも難しい→評判の教材や先生に課金⇒書けるようにならなかった(まじ裏切られた!)
伝わるでしょうか?『書けない⇒オワタ\(^o^)/』 の間に『なぜ書けないのか』のフェーズが挟まってますのでね!書けない理由は一つや二つじゃありません。私が書けない理由なんて、100個はザラにある。(実際ありましたよ!)そこを探して見つけて突き止める作業ってほんっとハードモードだから、「とりま教材買い足せば…」な~んてシンプル解を求めがちなんですが。それで10個解決したってまだ先がありますから…。
離脱・挫折のリスク
論文対策は100通余りの過去問と向き合う一大プロジェクト。だからこそ、真面目に勉強してる人ほど心の罠に落ちてしまうことがありそうです。
「先生の言う通りにできない」「一通りのことはやってみたけど上手くできない」あの方法もダメだった、これもダメだった。自分のどこがおかしいんだろう、何が足りないんだろう…。この手の落とし穴に落っこちて、心が折れて離脱する受験生も一定数いそう。
この時期をひたすらメンタル的に耐えて生き延びることも、具体的な勉強法と並ぶ重要テーマに感じます。
たぶんテンプレ通りにいかない
そもそも自分の学習が、テンプレ経過をたどるとは限りません。
たとえば私は、答案構成をずっと作れず、”起案もどき”を書き始めた時期が先でした。見よう見まねで起案していって、徐々に構成を組みかたが分かってきたので、構成→起案ではなくて、起案→構成なのです。
予備校の先生の解説で「まずは構成だけでも書いてみましょう」という話の印象が強かったので、このフェーズはホントに自分が今どんな状態にあるのか意味不明すぎる時期でした。
…という体験は、人に話せば「あ~そっちパターンだったのね」くらいで済んじゃう話だと思います。でもこの意味不明な時期は半年は続いて、その間「答案構成すら作れない私」と、ずっと思い続けていたのです。今の自分の状態が分からないって、すごく危険なことですよね。
悩みが拗れると…
「他の人はあの方法でうまく行ってるのに…」というのが頭をチラつくと、自分がおかしいのか、教材がおかしいのか、このメソッドがおかしいのか…と疑心暗鬼になってしまいます。そうすると手戻りが増え、教材を買い替えたりSNSを読み漁ったりあらぬ方向へ向かう結果、学習効率はダダ下がります。
「こうすれば絶対書ける」という、シンプルアンサーはないのに。
試験に向いてない⁉
上で『身近な人に普通のトーンで相談できるか』と書きました。テンション普通の時に小出しで人のアドバイスをもらっておくことは大事です。疑問と言う疑問がなくても「今こんな感じ~」と開示しておくことは一つの保険です。これを先延ばしにすると、何かのキッカケで気落ちしたときに一挙解決策を求めることになります。シンプルアンサーをひたすら求めてしまう。それが得られないと今度は、悩みが「自分に予備試験は向いていないんじゃないか、もう辞めた方がいいのか」みたいな重量級のものに変わってしまって、相談された方も「なぜそうなった⁉」っとびっくりすることに。
だいぶメンタル的な話になってしまいましたが、物事に挫折するときの状況を分解してくとこんな道をたどってるんじゃないかと…。
逆ギレしてもいいじゃない(笑)
つまり、とるべき行動としては…
なんだかんだ書いてみる。予備校の基礎問なり答練なりを出してみる。さんざんダメ出しされる。参考答案を読む。それをいったん認識する。
でもって「習ってないから書けないだけだし」ってスルーする!これでどうでしょう!
え?この問題は前にも見た?そんなときは「一度で覚えられたらただの天才だし」ってことで!
添削との向き合い方は、予備校によりさまざまあるのでいったん割愛しますが、要するに起案が軌道にのるまでのつまづき全般について、もう「仕方ない」と割り切る部分があっていいと思うのです。
仮装の敵をぶっつぶす!
三段論法ができてない?基礎知識が不十分?答案の型になってない??え?それができないから困ってるんですけど?(逆ギレ(笑)
いま自分はそういうフェーズなんですけど?みんなそういうフェーズありましたよね?なかったんですか?なかった人は参考にならないのでちょっと黙っててもらえますか??
…と、このくらい図太いメンタルでいてもバチは当たらない気がします(笑)。
私たちにできること
以上をふまえて受験生にできることは、正解かは分からなくても勉強をやめないこと。そもそも絶対的な正解なんてないのだし。そして雑音をシカトすること。モチベをそぐ情報を遠ざけること。人に相談すること。でもたった一人のたった一言に依存しないこと。そのためにも、できれば気軽に聞いて気軽に答えてもらうこと。
ある方法が上手くいかなければ、他の方法に切り替えてもいいけれど、「今までの自分は間違えてたんだ」とか、この教材はダメだ、あの予備校は違うとか…。そんなことは考えてもしかたないということ。
有益な情報さえ私たちのモチベをそぎ、ときには害になるということ。添削者の”かわいがり”に潰されないこと。
起案のお悩みターニングポイント
…本当に月並みですが、勉強をやめなければ「あ、ここが自分の書き初めだ」というポイントが訪れるはず。こっからバンバン書いてくぜ!っていう瞬間が。
その瞬間というのは、知識、文章力、構成力、筆力、思考力… さまざまなスキルがひっくるめて一定レベルをこえた時に「前より答案の形になってきた」という実感として訪れる気がします。
…というのは、サンプル数1の私の体験談。きっと起案に取り組む人の数だけ、違った突破口があることでしょう。
おわりに~楽しまなきゃ損~
さてさて避けては通れない論文対策なので、モチベを下げずに取り組みたい。モチベを下げないためには、周りの話を聞きすぎず、ちょっとした図太さも必要。ということで、少しはアンサーになっていましたでしょうか。
こんなに好き勝手書いたので、かくいう私はさぞかし充実した起案ができてるのかと思うでしょうか。充実…。毎日書いていて、そして毎回新鮮に「あ、初歩の初歩がやっと書けた」って気がしていますよ~!
そんな山あり谷ありの起案ライフですが、悩み過ぎず、お互い頑張っていきましょう。
2024/9/20追記
この投稿に対してXであ~じゃじゃまま~な(意図不明で思い出せない)コメントがつきました。自分の欠点も悩みも愚痴も隠すことなく書いたのが本投稿ですので、頂くコメントは私の欠点や悩みや愚痴に対する指摘として受け取ります。(発言の裏にある繊細な背景とか知りませんし。)
引用・コメントする際は「この人、他人の欠点や悩みに対して一方的にこういうコメントするんだ、へ~へ~へ~」…と受け留められることにご留意くださいな。同じ業界を志望する者同士、穏やかにいきたいですね。
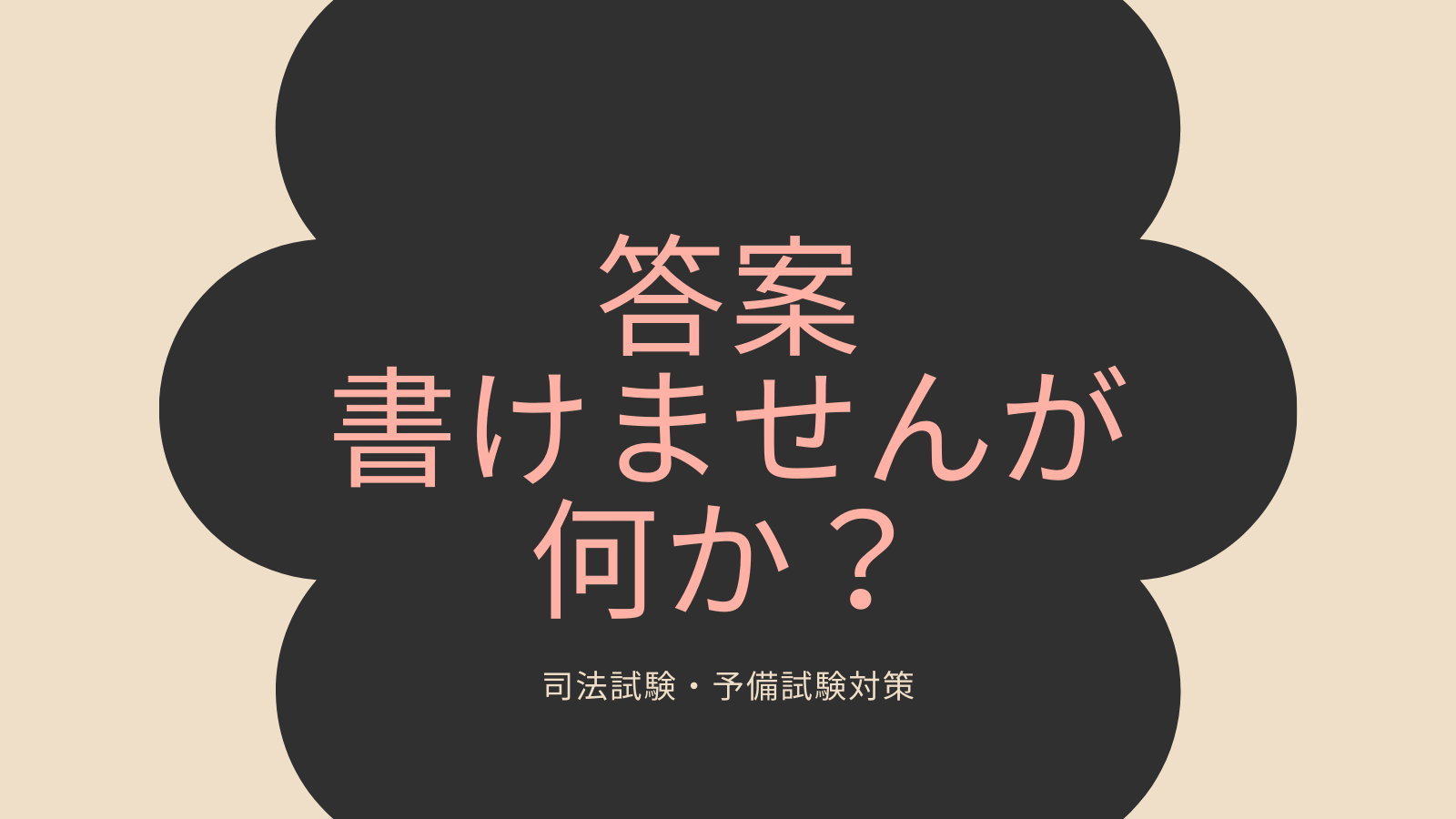
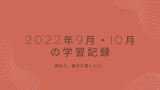
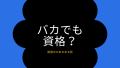
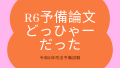
コメント